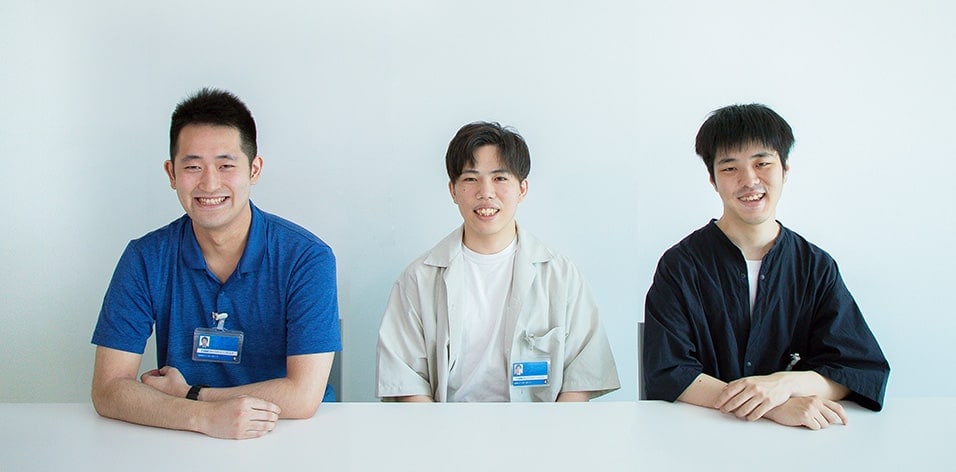CROSSTALK ARTICLE

-

S.F
2014年入社
次世代システム研究室 研究開発グループ
-

M.T
2014年入社
次世代システム研究室 研究開発グループ
-

L.W
2018年入社
次世代システム研究室 研究開発グループ
ブロックチェーンで新たな価値を創造する
皆さん様々な経歴をお持ちですが、GMOインターネットに入社した経緯を教えてください。
S.F わたしはインターネットベンチャーの責任者として1つの事業に深くコミットしていましたが、事業的にも技術的にも幅広く携わりたいと思うようになり、GMOインターネットに入社しました。
L.W わたしは前職で仮想通貨について知り、仮想通貨事業に携わりたいと思うようになりました。そういった中で会社を探していたところ、GMOインターネットに出会いました。
M.T わたしは新卒でこの会社に入社したのですが、SFさんと同様「幅広いサービスに携われる」「技術的にも幅広い分野にチャレンジできる」という点が決め手でしたね。
幅広い事業、というのが共通していましたが、具体的にどのような研究開発をしていますか?
S.F わたしたちのチームではアドテク開発支援、アプリ開発支援、ブロックチェーンに関わる開発を中心に、その他の分野でも事業化に向けた研究を行っています。 入社した当時はゲーム事業が盛り上がっていたため、ゲーム領域の開発支援をしていましたが、その後ウェアラブルデバイスやロボットに関わる開発、ブロックチェーンなどこれからトレンドになる技術にひとあし早く携わってきました。これからトレンドになる技術を一足早く検証し、ビジネスに生かすことができるか考えています。要素技術の研究だけではなく、ビジネスに生かすための応用研究という点がおもしろい部分ですね。現在は3名ともブロックチェーンに関わる業務に携わっています。
M.T ブロックチェーンに加え、グループ会社のサービスのバックエンド・フロントエンド開発にも携わっています。

ブロックチェーンのプロジェクトはいつ頃からどのような研究をしているのですか?
M.T 2015年末ですかね。ブロックチェーンとかビットコインというキーワードを耳にし始め、ビットコインが数万円という時から研究を始めました。ブロックチェーン自体がまだまだ発展途上の技術ですので研究を進めながら試行錯誤し、どうしたらサービスにつなげることができるのか考えながら研究・開発に取り組んでいます。直近ではGYENというステーブルコインを発行しました。
L.W 2018年の6月に入社した後すぐにマイニングのプロジェクトに携わり、マイニングの効率化に取り組みました。プロトタイプとして作ったものが効率化できることが証明できたのですが、その後ビットコインが大幅に下落した影響もあり残念ながらそのプロジェクトからは抜けました。その後GYENのプロジェクトを立ち上げ、MTさんがGYENの仕組み作り、私がそれを用いて多くの決済ができるような基盤の研究を行っています。 日本ではブロックチェーンの認知度が海外と比べまだ低いため、自分から海外の情報を取りに行き、理解をした上でチームメンバーに落としていくというのがとても難しいです。先ほどMTが言った通りブロックチェーンの技術は未成熟のため、海外から得た情報の信ぴょう性を確認する作業も必要ですし、色々な視点から考えながら情報を取り入れています。
S.F 次世代システム研究室では技術的なチャレンジをしながらサービスをいかにNo.1にしていくかということが大切なので、技術だけではなくビジネス的な視点も必要になりますね。
そんな次世代システム研究室だからこそ感じるやりがいはありますか?
L.W GYENは世界初となる米国銀行法規制を遵守し日本円と連携したステーブルコインですし、ほかにもGMOは様々なサービスでNo.1をいただいています。そういった世界初、No.1、というサービスに携われるのはとても貴重ですし、当社ならではのやりがいですね。
M.T 様々な事業に横断的に携わることができるのは本当に楽しいですし、常に新鮮な気持ちで仕事ができます。 また、新しい技術の研究だけではなくサービスに落とし込めることも楽しいですね。研究して論文を出して終わり、ではなく、それを形にして、誰かの笑顔のために技術を使えることがとても嬉しく感じています。
S.F 次世代システム研究室はグループ会社の技術支援を行っているため、いろんな人たちと一緒に仕事をできるということもあり、その中から新しい視点や気づきを得られることも醍醐味ですし、そういった人たちとお客様のためにどういったことができるのか議論ができることが楽しいですね。「技術のその先」をイメージしながら、日々試行錯誤しています。