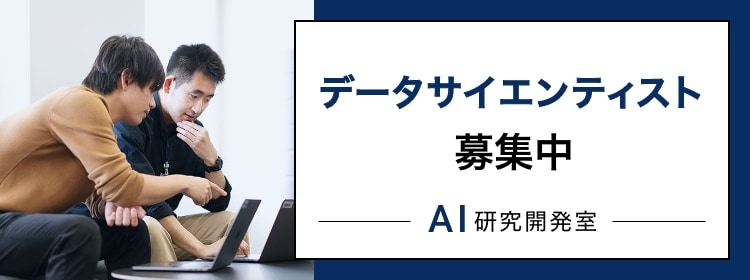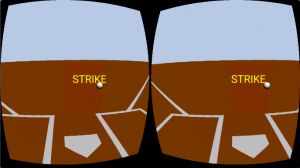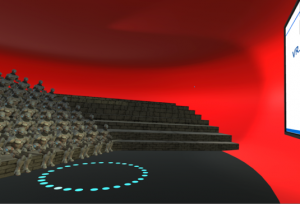2025.09.02
XRとアイトラッキング:進化の現在地と「視線×感情」の未来
こんにちは、次世代システム研究室のK.S.です。
私の最近の注目はXRになります。今回のブログでは、XRとアイトラッキングについて書いていきたいと思います。
なぜならば、XRのデバイス的進化とAIによるリアルタイム解析で、今後空間コンピューティングの世界が広がると考えるからです。
今回は、まずはサマリーの記事を書き、次回の記事で検証結果を実際に書いていきたいと思います。
近年、XR(Extended Reality)は「未来感のあるガジェット」から「実用的な体験デバイス」へと大きく進化してきました。特に、視線追跡(Eye Tracking)と 感情推定(Affective Computing) とAIが組み合わさることで、ユーザーの「見ている対象」と「感じていること」を同時に解析できる段階に到達しつつあります。本記事では、XRデバイスの進化を振り返りながら、その可能性を探ります。
XRの進化:ゴーグルから6DoFへ
XRデバイスは、この10年で大きく変化しました。
初期のHMD(ヘッドマウントディスプレイ)
現在のXRグラス
高解像度ディスプレイ、インサイドアウト方式のトラッキング、そして 6DoF(6自由度) により「空間の中を自由に移動して触れる体験」が可能になっています。

画像ソース:XReal
さらに、アイトラッキングセンサーの標準搭載が進み、「どこを見ているか」「どのくらい注視しているか」をミリ秒単位で計測できるようになりました。
これはユーザーインターフェースに革命をもたらすだけでなく、心理状態の推定にも応用可能です。
アイトラッキング+感情推定の分析例
例えば、30秒間の視線データを生成し、ユーザーが「ロゴ」「商品」「CTAボタン(購入エリア)」を見た際の挙動を分析できます。
1. ヒートマップ
視線の集中領域を可視化すると、商品エリアに視線が最も集まっていることが分かります。これは期待通りであり、実際の広告・ECサイトでも同様の傾向が見られます。

画像ソース: nngroup
2. 注視率と感情エンゲージメント
各エリアごとの 注視率(全視線時間に対する割合) と、視線中の平均的な「快・不快(Valence)」および「覚醒度(Arousal)」など算出することができます。
| AOI | 注視率 | 感情エンゲージメント(仮) |
|---|---|---|
| 商品 | 0.42 | 高め(興味喚起) |
| ロゴ | 0.10 | 低い(確認程度) |
| 背景 | 0.23 | 低い |
結果として、CTAを見ている間は快適さ(Valence)が上がり、覚醒度(Arousal)も高まる ことが確認できます。これは「購買直前の高揚感」をシミュレートしており、マーケティングやUX設計において非常に重要な指標になります。
XRの現在地とこれから
技術的には以下の進化が「現在地」と言えます。
- ハードウェア進化:軽量化、6DoF対応、アイトラッキング搭載
- ソフトウェア進化:AIによる視線解析、感情認識、UX最適化
- 研究応用:医療(ストレス診断)、教育(集中度計測)、広告(注視率+感情反応解析)
そして次のステップは、「ユーザーが見ている対象」と「その時の感情動作」をリアルタイムにAIが理解する」 という世界です。これが実現すれば、XRは「ただの表示デバイス」から「人間理解デバイス」へと進化します。
人の視線と感情を読み取るAIドリブンデバイスへと変化していくでしょう。
(例)アイトラッキングと感情AIで変わる教育体験:集中と好奇心をリアルタイムに捉えるXRの可能性
教育の現場では「いかに集中を持続させるか」「どのように好奇心を引き出すか」が永遠のテーマです。従来は学習者の様子を教師が観察し、進行を調整するしかありませんでしたが、XR+アイトラッキング+感情AI によって、この課題は新しい解決策を得つつあります。
学習者の「集中」と「好奇心」をどう測るか
人間の集中度や好奇心は、行動や表情からある程度推測できますが、より直接的な手がかりが 視線 です。
- 集中している時 → 視線は狭い範囲に長くとどまり、注視時間(Fixation duration)が伸びる。
- 興味を持った時 → 新しい対象に素早く視線を移し、視線移動(Saccade)が活発になる。
- 退屈や疲労 → 視線が宙をさまよい、まばたき頻度が増える。
これらのパターンをリアルタイムで解析することで、学習者の「今」の状態を数値化できるようになってきました。
XR学習環境における応用シナリオ
1. 集中度に応じて教材を変える
もし学習者が「集中していない」とAIが判断したら、教材を短いクイズに切り替えて注意を取り戻す。逆に、集中が高まっている時は難易度を一段上げる。
2. 好奇心の瞬間を捉えて映像を分岐
例えば歴史の授業で生徒が「戦国時代の武器」に視線を注いで興味を示したら、その場で関連する3D映像や補足解説を提示する。視線が選択肢になる新しいUXです。
3. 集団学習での「集中度マップ」
教室全体のアイトラッキングを集約し、どのスライドや教材部分に視線が集中しているかをリアルタイムで教師に提示。授業の「熱量」を可視化できます。
技術的背景:6DoFとAIの役割
この仕組みを支える技術のポイントは大きく3つです。
– 6DoFトラッキング
学習者の頭部と身体の動きを空間的に把握し、視線と組み合わせることで「実際にどの対象を見ているか」を正確に捉えます。
– アイトラッキング+感情AI
視線の停留、瞳孔の変化、瞬きの頻度から「集中度」や「覚醒度」を推定。機械学習モデルによって学習者ごとの特性に適応可能。
– リアルタイム教材生成
AIが学習者の状態を解析し、その場で教材を選択・生成。将来的には生成AIと教育XRが統合し、無限に分岐する学習シナリオが実現します。
学習効果の可能性
研究段階の結果ではありますが、以下のような効果が期待されています。
– 集中が続かない生徒のリカバリー率向上
– 興味関心に沿った学習でモチベーションの維持
– 学習時間あたりの知識定着度の向上
つまり、教育は「教師が一律に進める」ものから、AIが学習者ごとにリアルタイムで最適化するパーソナルラーニングへと進化していくのです。
結論:AIが「好奇心のスイッチ」を押す未来
従来の教育は「集中するのは生徒の努力」という前提でした。
しかしこれからは、AIが学習者の集中や好奇心をリアルタイムに察知し、教材そのものを変えていくことが可能になります。
XR+アイトラッキングは、学習者の「心の動き」を読み取り、最も効果的な学びの瞬間をつくり出すインフラになるでしょう。
次世代システム研究室では、グループ全体のインテグレーションを支援してくれるアーキテクトを募集しています。インフラ設計、構築経験者の方、次世代システム研究室にご興味を持って頂ける方がいらっしゃいましたら、ぜひ募集職種一覧からご応募をお願いします。
グループ研究開発本部の最新情報をTwitterで配信中です。ぜひフォローください。
Follow @GMO_RD